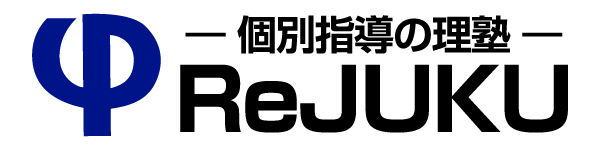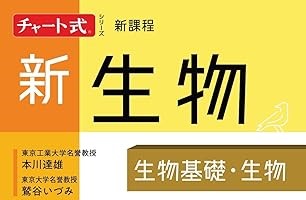理塾で実践している、高校生物の勉強法を伝授します。
高校生物の勉強法は、次の通りです。
理塾で採択している高校生物教材はコチラ。
◆(参考書)チャート式生物<数研出版>
◇(基本)生物基礎リードlightノート<数研出版>
◇(標準)生物リードα<数研出版>
◇(発展)重要問題集<数研出版>
◇(難問)思考力問題精講<旺文社>
(0)生物の参考書を準備する
教科書と資料集を使っても良いのですが、大学受験に必要なあらゆる情報が網羅された参考書を一冊持っておくと、重宝します。

チャート式生物は、標準的な問題集であるリードαや、発展的な問題集である重要問題集と同じ、数研出版が発行しているので、相性は非常に良いですから、オススメの一冊です。
これから進める部分を予習としてあらかじめ読んでおくのも良いですし、問題集の解説だけではわからないところを詳しく読み込むのも便利です。
(1)生物基礎を学習する
教科書と高校で配布された教科書傍用教材(リードαやセンサーやセミナー)で、生物基礎の学習を進めましょう。
暗記要素が多く、典型的な問題しか出題されないため、ゆっくり進める必要はなく、すべて丸暗記するつもりで取り組んで構いません。
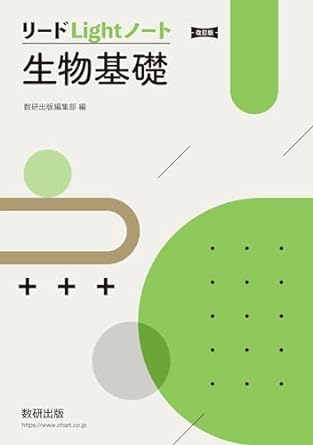
1問10分として、150問程度あるため、合計で1500分ですから、25時間ほどで一周目が終わるでしょう。
暗記の度合いや習熟度にもよりますが、不安な人は二周目をしてから次のステップに進みましょう。
(2)教科書内容を把握する
教科書を解説してもらったり読んだりしたうえで、高校で配布された教科書傍用教材(リードαやセンサーやセミナー)で該当範囲の問題を解きましょう。
チャート式生物と同じ出版社であるリードαがオススメです。Amazonでも入手することが可能です。

むしろ、基本的な用語の意味を覚え、正しく記述できるように、あらゆる範囲を一通り学習をするのがポイントです。
この時には、応用問題や発展的な問題はできなくても構いません。
生物は網羅的な知識がまず要求されるので、少ない知識で応用問題を解くことは非効率的ですから、まずはとにかく知識を増やしましょう。
もし独学で進める場合は、教科書ではなくチャート式(生物)を利用しても構いませんが、簡単な内容も難しい内容も同じように併記されているため、指導者について「ここは絶対に覚える」「ここは後回しでも良い」などアドバイスした方が良いでしょう。
進め方にもよりますが、必要な時間の目安は、一周目で80時間ほどです。
二周目で20時間で、二周すれば、だいたいのことは頭に入ってくるはずです。
そしてこの100時間あれば、共通テストで6割ほど、平均点は取れるレベルに到達します。
産近甲龍未満(偏差値50に達しない)の大学を狙うのであれば、この教材を何周も演習して、内容をほぼほぼ頭に叩き込めば、過去問を解いても合格ラインの7割程度が狙えるはずです。
※定期テスト対策としては、この段階までで良いでしょう(教科書と傍用教材を正しく使用すれば、他は必要ないです)。
※理解度は人によって差があるため、三周四周が必要になる人もいます。
(3)重要問題集を解き進める
重要問題集は、発展内容を攻めるという意味もありますが、実際には「受験で典型的に出題されるパターンが網羅されている」ということが最大の特徴です。

(必)マークはすべて取れるようにしましょう。
必要な時間の目安は、1問当たり20分程度かかるとして、一周目で40時間ほどです。
二周目は半分ほど時間がかかるとして、二周目で20時間です。
そして、この60時間ほどあれば、共通テストで8割ほど、産近甲龍でも十分戦えるレベルに到達します。
(準)問題は、生物を得意科目にするには必須です。
必要な時間の目安は、1問当たり30分程度かかるとして、一周目で20時間ほどです。
二周目でも要点を丁寧に再確認すると、さほど時間は短縮できないことが多いので、二周目で20時間です。
そして、この40時間ほどあれば、共通テストで9割から10割、関関同立でも十分戦えるレベルに到達します。
国公立大でも、大阪公立大クラスであれば、これで十分です。
合計100時間を重要問題集に費やせば、おおよそどんな問題でも、手が出せる状態になるでしょう。
要するに、100時間ほどで基本的な学習が終わり、200時間ほどで発展的な学習が終わることになります。
※国公立大と関関同立レベル以上を求める場合は、この段階まで必要。
(4)思考力問題精講
旧帝医大を目指す場合は、重要問題集だけでは少し不足する部分が出てきます。
その場合は、思考力問題精講に取りかかりましょう。
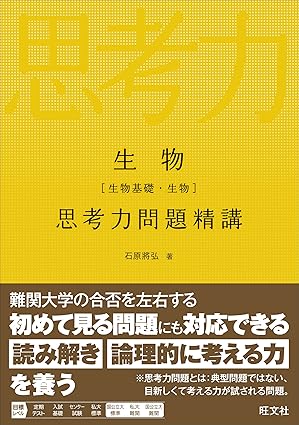
このレベルになると、もはや作業ではないため、必要な時間の目安は人によって大きく異なります。
また、独学で扱える問題集ではないため、旧帝医大レベルの実力を持った個別指導もしくは家庭教師を頼ることが前提です。
浪人と戦うつもりで、じっくりと時間をかけて、マスターするようにしましょう。
高校生物を効率的に学習するなら、勉強方法にも詳しく、医大生講師が教える理塾にお任せ下さい(リモート授業も対応できますから、遠距離授業もお任せ下さい)。